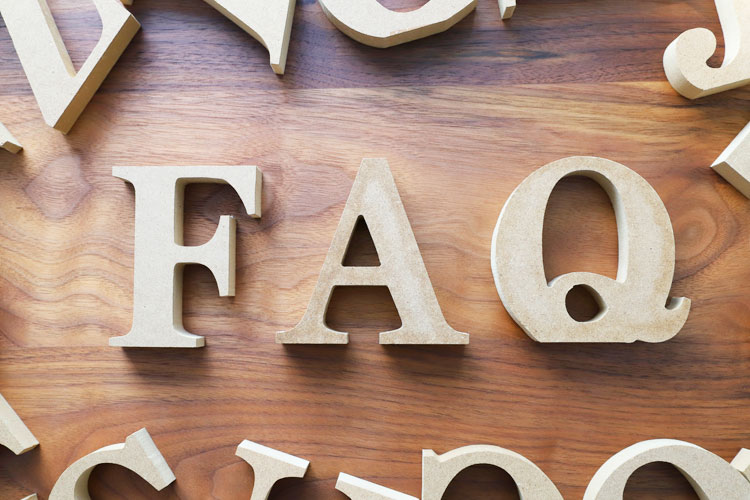
患者様からいただく質問の中でも、よくある質問を、まとめてご紹介しております。是非、参考になさってください。
また、ご不明な点など、遠慮なく当院までご質問ください。
よくある質問カテゴリー
診療について
当院について
当院の診療と診療方針について
病院に行きたいけれどコロナウィルスや風邪をもらいそうで怖いのですが、、
当院では問診の時点で発熱の患者様と一般と患者様との導線を分けておりますのでご安心ください。
発熱の患者様は院外でお待ちいただき、最優先に医師が往診しております。
また、院内感染対策として3密を避けるため、院内の椅子の数を減らし、混雑時は外出のご協力お願いをしております。
診療方針について
当院ではなるべく通院が最小限になるようにしっかり検査をしてなるべく長期処方をこころがけています。花粉症治療は初回は2週間処方ですが、内服が身体にあうようであれば1ヶ月処方しております。
鼻の低侵襲の日帰り手術にも力をいれており、内服でも効果のない通年の鼻つまり、くしゃみ、鼻汁、いびき、睡眠時無呼吸の方は是非ご相談ください。
予約について
デジスマアプリがなくても予約できるの?
クリニックwebから簡単な入力で予約できます。
デジスマアプリを利用すると次回予約が入力を省略できるため楽になります。
(アプリは必須ではありませんがなるべくご利用ください。)
予約後にご自宅でアプリより問診を入力していただけますと待ち時間を短縮できます。
(任意入力で必須ではありません)
パソコンやスマホが苦手でどのように予約したらいいかわからない
予約ができない方は今までどうり診察後にクリニック受付で次回予約を取れます。自宅からクリニックまで電話でもスタッフが代理で予約をお取りします。
急に具合が悪くなったが日時指定の予約が空いていない場合どうしたらいいか
予約が入らない方のために当日予約枠を午前中30分間、午後に30分間用意しております。午前分の当日予約は当日の朝9時から、午後の当日予約が当日の午後15時から受付開始しております。半日に10名のみの受付ですので、予約人数に達した時点で受付が終了となります。
当院の定期的にかかりつけの患者様で緊急と判断される場合は予約なしでも診察しますのでご安心ください。(予約優先となるため待ち時間は長くなる可能性があります)
オンライン診療はどうなるの
2023年12月より完全予約制となるためコロナ禍で実施していましたオンライン診療は終了となります。
日帰り手術を希望しているがどうしたらいいの?
星長院長と川野副院長の診察日の午前と午後に<手術希望の方>専用の予約時間帯を確保していますのでご安心ください。
日時指定予約とは
従来の当院の予約は電話予約、受付予約、当日WEB予約、当日順番待ちなど予約が混在しており予約をしていても2時間待ちが頻発するなど非常に待ち時間が長く患者様のストレスがありました。
そのため当院は2023年12月より完全予約制に変更します。
デジスマ診療で予約することにより、クリニックで受付してから会計までの時間を極力短縮することに努力いたします。(従来の3時間以上のクリニック滞在時間から1時間以内を目指します)
日時指定予約をしていても急患対応などでお待たせする場合もありますが何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
インフルエンザ予防接種は?
従来どうり予約不要で診察時間に受付まで来院ください。
デジスマ予約枠はどういう運営か?
初診の方はしっかり診察するため5分 再診の方は2分、薬のみ希望(CPAP定期フォローを含む)の方は1分の予約枠です。
たとえば7分の予約枠が空いている場合初診の方が1名入ると、残りは2分のため再診の方は1名のみもしくは薬のみの方は2名予約ができるシステムです。
そのため初診枠が空いていない場合も再診枠は空いている可能性はあります。再診枠で予約の方は詳しい検査はできません。
支払いについて
クレジットカード・キャッシュレス決済は可能でしょうか?
現在は、現金での対応の他、以下でのお支払いが可能となっております。
PayPay、クレジットカード(VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、DISCOVER)利用可能です。
全て保険診療でしょうか?
ほぼすべての診療が保険診療です。
例外として、インフルエンザ予防接種、コロナウィルス抗原検査(手術前検査)、保険会社の診断書は自費となります。
その他の質問について
駐車場はありますか?
クリニックモールに無料駐車場16台、クリニック斜め向かいに提携駐車場に18台あります。(提携駐車場はクリニックから1時間分のコインをお渡ししています、1時間を超えた場合には有料となります。)
大人の待合室とは?
耳鼻咽喉科は老若男女様々な患者様がこられます、難聴や耳鳴りの高齢者は内耳が過敏のため、子供の泣く声などが不快に感じることもあると思います。
そのため当院では、子供用のキッズスペース、通常の待合室以外に、大人専用のゆったりとした静かな待合室や補聴器相談室を用意しております。
インフルエンザについて
インフルエンザワクチンの効果について教えてください。
インフルエンザワクチンをきちんと接種したのにインフルエンザにかかってしまう人は少なくありません。
文献報告によるとインフルエンザワクチンの有効率は60~30%といわれています。これは逆にいえばワクチンを接種していても40~70%の人はインフルエンザにかかってしまうということになります。
ただし、ワクチンをうっているとインフルエンザになっても高熱が抑えられたり、脳炎や肺炎の合併症が起り難いと言われています。
また、罹患した後のインフルエンザ治療薬については副作用が報告されており、そういった意味でも罹患する前にワクチンを接種する必要性は十分にあります。
ワクチンの有効期限について教えて下さい。
ワクチンは接種後2週間目頃より効果があり、その効果は3~6ヶ月後まで続くとされています。
日本のインフルエンザ流行期は12月から3月ですので、10~11月に接種することが最も効果を期待できると思われます。
また、基本的に大人の方は、ワクチン接種は1回ですが、インフルエンザの流行期に追加の接種をすることでさらに免疫力を高めて、より高い予防効果を期待できるという報告もあります。
妊娠中・授乳中の場合の接種について教えて下さい。
インフルエンザワクチンは不活化ワクチンであり、胎児への影響はありません。
妊婦の場合、インフルエンザに罹患した際に合併症をきたしやすいといわれています。
そのため、自然流産を起こしやすい妊娠初期は避けて、妊娠12週以降の接種が勧められます。
授乳中の方への接種ですが、インフルエンザワクチンの成分が母乳に移行する量は極めて微量で、乳児への影響はほとんどないと考えられます。
ご両親自身がインフルエンザを予防することで乳児への感染を防ぐという意味で、ご両親へのワクチン接種については推奨されます。
インフルエンザウイルスとは何ですか?
インフルエンザウイルスは低温と乾燥を好むため、毎年冬になると猛威をふるいます。特に子供や老人では重症化して生命をおびやかすこともあり、早期の診断と治療が重要です。
一般的には急な高熱で発症しますが、最近では37度台でも調べるとインフルエンザのことがあり、冬場の発熱は要注意といえます。現在では10~15分でわかる迅速検査キットがあり、A型、B型の判定も可能です。
最も多く使われてきた治療薬にタミフルがありますが、10代の患者様での異常行動が報告され、最近ではリレンザという吸入タイプのお薬もよく用いられています。しかし、リレンザもまったく安全というわけではなく、患者様の年齢、体力を考慮して治療法が選択されます。
解熱剤を使用しなくても自然に熱が下がり、そこから2日間たてば他人への感染の心配はなくなり、学校や幼稚園、保育園への登校・登園も許可されます。
但し、熱が下がってもインフルエンザの影響で鼻や咳がしばらく続くことがあります。
